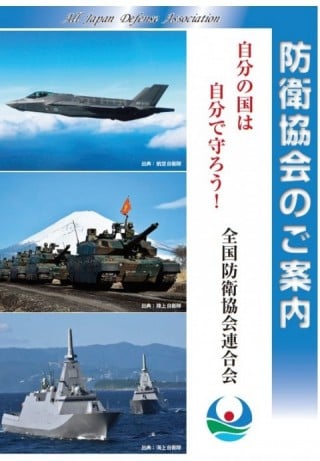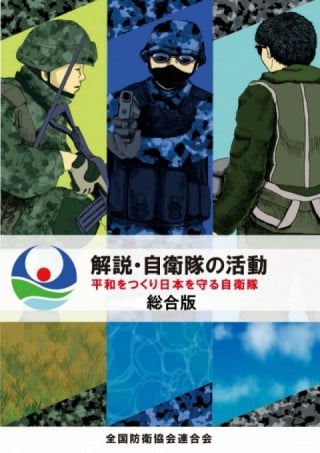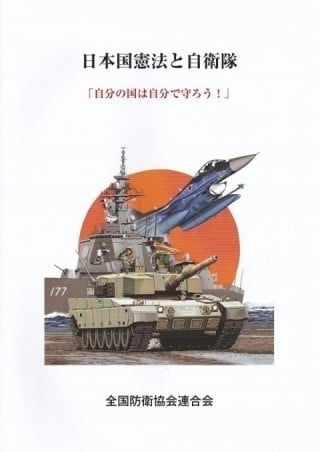防衛時評
令和7年
常任理事 山田 真史 防衛協会会報第170号(7.4.1)掲載
昨年の秋、ネット上にこのような記事を見つけた。「自衛隊の新規採用に行き詰まり(swissinfo.ch 2024/09/23)」。要約すると、「防衛省は自衛官の採用計画に対する昨年度の『達成率』が創設以来で過去最低を記録。手厳しい論調を載せたのは独語圏の日刊高級紙NZZ。『日本の自衛隊は新兵獲得に失敗している。安っぽいPRではなく、東アジアで高まる安全保障上のリスクを訴えた方が得策だ』と断言した。若年層人口の減少などにより新規隊員を確保する努力は避けては通れないものの、これまでの採用キャンペーンには『絶望的と思えるものもある』と指摘。髪型の選択の自由化やセクシャル・ハラスメント被害者へのカウンセリングサービスなどが若者を誘致する原動力にほとんどなっていない。中国、北朝鮮の軍事的圧力や大国ロシアとの国境問題などといった『周辺の安全保障状況は悪化しており、日本は近隣諸国からの脅威に対してもっと武装しなければならないという核心的なメッセージを政治指導者が伝えられない限り、(新規採用に向けた)こうした努力が実を結ぶことはないだろう』と断言した」。我が国の致命的な課題を他国の報道に、しかも永世中立を国是としているスイスのメディアに本質的な問題点を指摘されていることに衝撃を受けた。当然、自衛隊における各種ハラスメント防止はとても重要であり、そのことを否定しているわけではないのだろう。現在、政府主導で自衛官の処遇改善が検討・実施されているが、これまで処置されていなかった重要な部分にやっと焦点が当たっているに過ぎない。しかしながら、当記事の指摘にある「東アジアで高まる安全保障上のリスク」という指摘については、「憲法改正」にも関連して来よう。加えて、その現状を「日本国民が共有する」ことにも繋がっている。先進国における安全保障に関する事柄の「国民への共有」という観点で見ると、米国は国家防衛教育法に基づいた教育を実施している。また、隣国の韓国や北欧のフィンランド、デンマーク、ノルウェー及びスイスは徴兵制を採用している。これらの国々の18才以上の若者は全国民が国防教育を受けていることになる。一方、隣国である中国は2024年に国防教育法を改正し、小学生から国防意識を養い、一般大学では軍事訓練を義務付けたと伝っている。どの国の国防教育も戦争を推奨しているわけではなく、自国の安全保障に関する常識を付与し、自国を守る事の尊さを教え共有しているのに他ならない。本誌はこうも続けている。「また日本は第二次大戦後、平和憲法の下で交戦権を放棄し、反軍国主義は一種のエチケットとみなされてきた」。今、ウクライナの悲惨な現状を観るにつけ、将来の我が国の平和を担保するためには、安全保障に係る「国民の理解」をさらに深める事が必須であろう。「国の興亡は戦争の勝敗によりません。その民の平素の教養によります」(内村鑑三)「自分の国の平和は自分の手で守る」という意識を芽生えさせ育てるためには学校教育の中に、その機会を設けるための施策と実行が急がれる。
(元航空支援集団司令官)