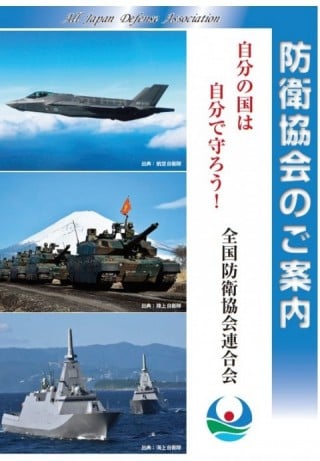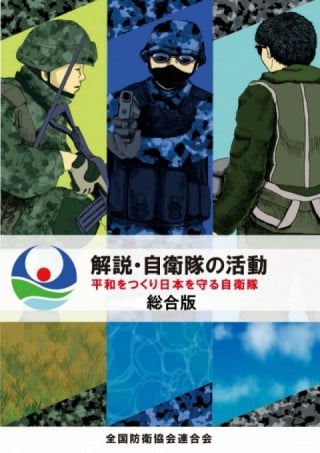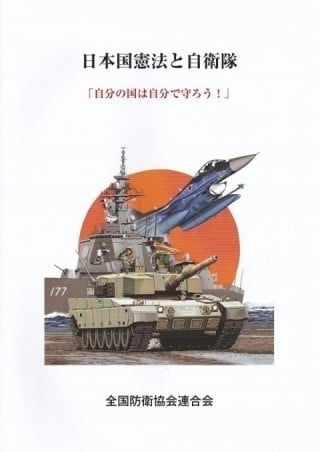一筆防衛論
令和7年
常任理事 岸川 公彦 防衛協会会報第170号(7.4.1)掲載
ウクライナには、これまでの度重なる紛争の影響により、広範囲にわたり大量の地雷・不発弾が残されており、特に戦闘が激しかった東部のドンバス地方や南部のクリミア半島周辺では、地雷や不発弾による被害が後を絶たない状況です。
これに対し、ウクライナ政府はもとより、多くの国や国際機関が資金援助や技術提供を行い、それらの除去活動を行っています。
このような中、日本も、長年にわたりアジア地域を中心に地雷・不発弾等の処理活動における支援活動を行うとともに、これらのノウハウを他国等と共有してきました。特に、カンボジアにおいては、JMASをはじめ多くの日本のNGOが、同国の政府機関として地雷処理活動を統括する「カンボジア地雷処理センター」(CMAC)と連携し、地雷・不発弾等の処理活動やこれらの活動に必要な技術指導、訓練や機材の提供を行い、同国の復興に多大な貢献を行ってきました。
これらを受け、現代では、CMACが主体となって、ウクライナの地雷・不発弾等の専門家に対して、長年にわたり日本から学んだ経験と知見を活かし、かつ日本から提供を受けた地雷探知機などを用いて、各種訓練等を行い、ウクライナの復興と安全確保に貢献しています。
これら一連の日本とカンボジアによる支援に対しては、ウクライナ政府からも大きな期待が寄せられているところですが、他方で、未だ戦争が継続している同国における日本の人的な貢献には諸処制約があり、これらへの対応が大きな課題となっています。
このような制約下、日本が行う支援施策として、①CMACなど第3国の機関やNGO等を介した間接的な支援や②ポーランドなどの第3国/地域における支援などが検討されており、既に日本国内におけるウクライナ緊急事態庁要員に対する教育などが実行されています。
このような中、本年、日本において、世界各国の政府代表者や国際機関、非政府組織、民間企業の参画を得て、経済再建やインフラ復興などについて議論する「ウクライナ復興支援会議」が開催される予定であり、日本はその開催国としてリーダーシップの発揮が期待される中、地雷・不発弾等の処理分野において、我々の活動の真価が問われることとなります。
(元陸自中部方面総監)