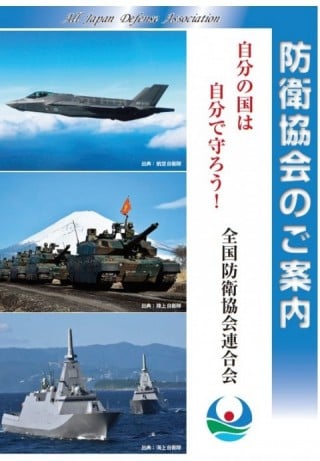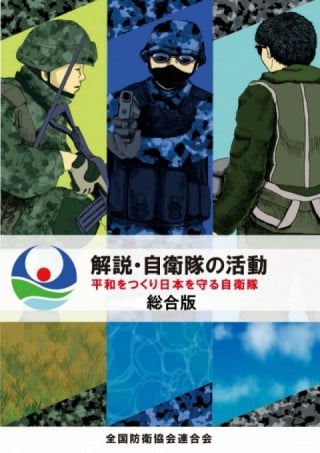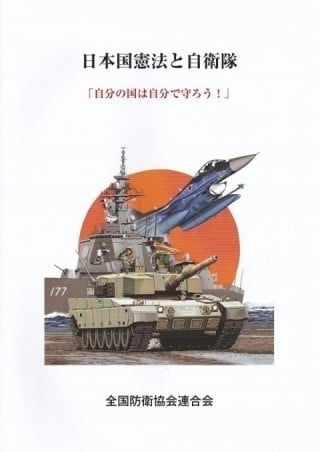オピニオン・エッセイ
エッセイ
陸上自衛隊と仏陸軍の間で実施している共同訓練があります。それは「ブリュネ・タカモリ」です。人命を掛け合わせたものであり、「ブリュネ」とは、江戸時代、軍事顧問として来日した陸軍参謀総長・ジュール・ブリュネに因んでいます。軍事技術等を伝えるとともに自身も幕府軍として戦った人物であり、ハリウッド映画「ラストサムライ」のモデルになった人物です。私にとっては年末時代劇スペシャル「五稜郭」(1989年)で俳優の岡田真澄さんが演じていた記憶が残っています。一方「タカモリ」とは初代陸軍大将を務めた西郷隆盛に因んでいます。
あまり耳馴染みのないコードネームですが、それもそのはず、2023年に第一回目が行われたばかりと日が浅い訓練です。その記念すべき第一回目の舞台となったのは、仏領ニューカレドニアでした。フランスは、南太平洋に領土または特別共同体となる地域を有しています。よって、中国の海洋進出は決して他人事ではないばかりか、脅威ですらあります。こうしたことからNATO加盟国の中では、「自由で開かれたインド太平洋」具現化の中核となっています。そして仏領ニューカレドニアには、約2000名の陸海空軍を駐留させています。
2024年9月8日から20日にかけ、王城寺原演習場(宮城県)及び岩手山演習場(岩手県)等において、2回目となる「ブリュネ・タカモリ24」が実施されました。陸自側は第9師団から第39普通科連隊を中核とした師団隷下部隊約100名、仏陸軍側は第6軽機甲旅団から選抜された約50名が参加しました。
仏第6軽機甲旅団ですが、緊急展開即応部隊であり、世界中どこへでも駆け付けて戦うことが出来る機動力の高い部隊です。湾岸戦争やマリ共和国でのイスラム武装勢力とのゲリラ戦など、実戦経験は豊富です。太平洋地域で何かあれば、間違いなく中枢となり戦う部隊となるでしょう。そして、外国人部隊LEGION ETRANGEREの比率が多いのも特徴です。
訓練の目的は、対ゲリラ・コマンドウ作戦に係る戦術技量の向上を目指すことにあり、中隊以下の小隊や分隊等の小規模部隊の戦術行動訓練及び実弾射撃訓練を実施します。大きく2つのパートに分かれており、8日の訓練開始式の後、9日~14日までが機能別訓練、16日~19日までが総合訓練となっていました。私は総合訓練を取材しました。
まず、王城寺原演習場にて敵部隊の捜索が行われました。最終的に敵は市街地に潜伏。これを日仏で掃討すべく、市街地戦闘訓練場を使っての実戦的な訓練となっていました。敵の捜索には日仏部隊ともドローンを活用しており、新しい戦い方を垣間見ました。戦闘中、陸自隊員が敵の人質となり、救出する場面もありました。仏軍部隊は、ゲリラ戦の経験は豊富であり、実戦で培ったノウハウは陸自部隊に大変参考になったことでしょう。
追い詰められた敵は岩手山地区へと移動しました。そこで、日仏両部隊は、陸自ヘリを使い岩手山演習場へと空中機動作戦を展開し追撃します。そして同演習場にて総合戦闘射撃が行われました。日本の演習場で、仏軍兵士が実弾射撃訓練を行うのはこれが初めてとなります。後方地域から陸自砲迫の火力支援を受け、日仏部隊が前進していきます。突然現れる敵に見立てた標的を倒してはさらに前進していきます。16式機動戦闘車による火力支援もありました。
第6軽機甲旅団長・ヴァランタン・セイラー准将は、記者会見にて「今回の訓練は日本とフランスの協力強化の一端をなすものだ」と締めくくりました。すでに2025年の開催も決まっているそうです。