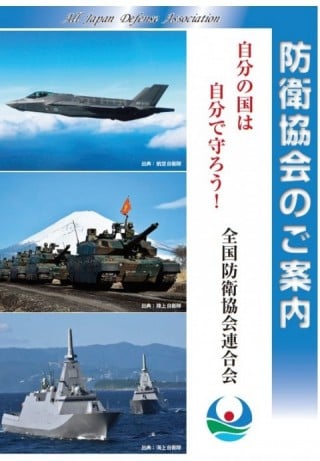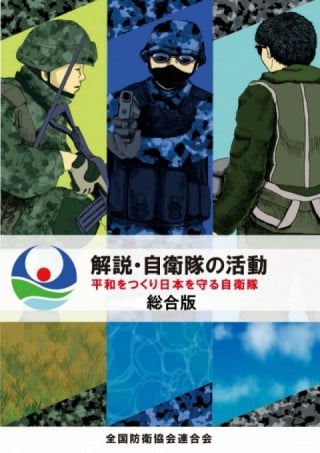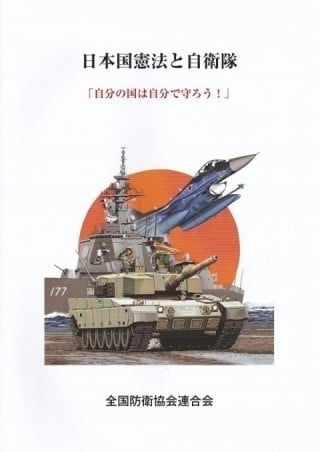定期総会
令和6年 防衛協会会報第167号(6.7.1)掲載
全国防衛協会連合会第35回定期総会
「自分の国は自分で守る」という強い気概の啓発
全国防衛協会連合会(大宮英明会長)は5月27日、ホテルグランドヒル市ヶ谷(東京都新宿区)において第35回定期総会とその関連行事(表彰式、講演会、懇親会)を開催した。
総会に先立って表彰式を行い、協会の発展に功績顕著な個人・団体を表彰した(下段に詳細記述)。
総会には連合会役員及び都道府県防衛協会・自衛隊協力会等の会長ら約50名が全国から参集した。総会では、8年の長きにわたって在任し、連合会の発展に多大の貢献をされた金澤博範副会長兼理事長が退任し、後任の理事長には、島田和久氏(元防衛事務次官)が後任の副会長兼理事長に選任された。
定期総会
総会では次の6項目の案件が審議され、全て原案通り承認された。
1 令和5年度事業報告
2 令和5年度収支決算書
3 令和6年度事業計画(案)
4 令和6年度収支予算書(案)
5 役員人事(案)
新任又は交代者として15名の役員を新たに選任(特別顧問1名、副会長兼理事長1名、副会長3名、常任理
事6名、理事3名、監事1名) 【新体制は本ホームページの役員欄参照】
6 「令和6年度防衛問題に関する要望書」(案)【下に全文掲載】
令和六年度防衛問題に関する要望書
全国防衛協会連合会は、各都道府県防衛協会の連合体として「防衛意識の高揚」と「自衛隊への支援・協力」を目的に活動しています。共通の目的を持つ民間有志の集まりとして、国民としての目線から、防衛問題に関して要望するものです。
第一点 憲法改正
我が国を取り巻く安全保障環境が近年一層厳しさを増す中、関係者の努力は並大抵のものでないことを十分理解し、応援しています。その一方で国民の国防意識や自衛隊に対する理解は、残念ながら決して高くはありません。
そのため、国防に関する記述が欠落している憲法をできるだけすみやかに改正して、国防の中核たる自衛隊の位置づけを明確化することを要望します。憲法改正により、国民の自らの国を守るとの国防意識が高まるとともに自衛隊に対する理解が格段に進むものと確信します。
第二点 国防意識の高揚を図るための各種施策の充実
憲法改正と同様に、国防のさらなる充実を図る上で、国民一人一人が、国家に対する誇りと国防に取り組むことの重要性について、正しく理解することは、極めて重要です。
そのため、学校教育の場はもちろんのことあらゆる機会を通じ、国防意識の高揚を図るための各種施策の充実を要望いたします。これにより、自衛隊に対する理解もさらに促進するものと確信します。
第三点 自衛官の処遇向上
自衛官及び自衛隊部隊等に対する施策は、逐次充実してきており、関係各位のご努力に深甚なる敬意を表します。しかしながら大変なご努力にもかかわらず、自衛官の処遇は、諸外国軍人の処遇と比較してもなお不十分であり、国家として自衛官の責任感・使命感に応えきれていないと感じます。自衛官の特殊性を十分に考慮した各般の処遇を改善することで、現職自衛官の任務遂行に国家として報いると共に、大変に困難な状況にある自衛官募集の問題を解決することにもつながると確信します。
以上、要望します。
令和六年五月二十七日
全国防衛協会連合会 会長 大宮 英明
講演会
総会終了後、中国政治を専門とする前防衛大学校長・慶應義塾大学名誉教授の國分良成氏による「中国情勢と米中・日中関係」をテーマとした講演が行われた。まさに時宜を得たテーマであり、約100名が高い関心をもって聴講していた。【下に要旨を掲載】
懇親会
講演会終了後は、懇親会が催され、松本尚防衛大臣政務官をはじめ、吉田圭秀統幕長・上田和幹陸幕副長・酒井良海幕長 ・内倉浩昭空幕長等の防衛省・自衛隊の最高幹部、講師の國分良成氏、友好団体の会長・理事長等多数の来賓が足を運ばれ、約80名の参加者を得て懇親を深めた。
懇親会では、大宮会長の挨拶、島田和久新理事長の就任挨拶に引き続き、松本政務官と吉田統幕長による祝辞、来賓・表彰状受賞者の紹介、木原稔防衛大臣からの祝電披露と進み、岩﨑茂隊友会理事長による乾杯のご発声で歓談がスタート。そして、宴もたけなわの中、全国防衛協会連合会青年部会の垣内猛会長による万歳三唱の音頭でお開きとなった。
大宮英明会長挨拶
懇親会に入る前に、先般の鳥島沖におけるヘリコプター事故により志半ばにして殉職された隊員の方に謹んで哀悼の意を捧げると共に、未だ行方不明となっている隊員の皆様が、一刻も早く発見されますよう心からお祈り申し上げます。
本日は、全国防衛協会連合会の懇親会に公務ご多忙のところ、防衛大臣政務官 松本尚様、統合幕僚長吉田圭秀陸将をはじめ、防衛省・自衛隊、友好団体並びに特別会員の皆様方など多数ご参加いただき誠に光栄に存じ、厚く御礼申し上げます。
先程の定期総会で、令和6年度事業計画及び収支予算と役員人事が承認され、令和6年度活動が本格的に始動することとなりました。
また、当連合会に貢献された14名の方に表彰状を、1団体に感謝状を贈呈させていただきました。
講演会では、前防衛大学校長・慶應義塾大学名誉教授の國分良成先生に「中国情勢と米中・日関係」と題して貴重なご講話をいただき、誠にありがとうございました。
さて、我が国周辺では軍備増強が急速に進み、力による一方的な現状変更の圧力が高まっており、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。
このような中、自衛隊の皆様方は、わが国の安全保障という崇高な任務を遂行しつつ、国内外において災害派遣などで活動されており、その献身的なご活躍は、国民の自衛隊に対する信頼と期待をますます高めることとなっております。
また、岸田総理も本年4月1日の米国上下両院合同会議の演説の中で「今この瞬間も、任務を遂行する自衛隊と米軍の隊員たちは、侵略を抑止し、平和を確かなものとするため、足並みをそろえて努力してくれています。私は隊員たちを賞賛し、感謝し、そして隊員たちが両国から感謝されていることが、私たちの総意であると知っています。」と、自衛隊員の皆様の活動に対して感謝と敬意を表しました。
当連合会としては、現下のウクライナが示すように国民一人一人が、「自分の国は自分で守る」という強い気概を持つことこそが肝要であり、それを啓発するのが、防衛協会の役割であると認識しております。
今後とも「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務める」という自衛官の皆様の熱い心に応えることができるように、時代の風を感じながら前向きに活動し、会の目的である「防衛意識の高揚」と「自衛隊への支援・協力」を推進して参りたいと考えております。
講演会 講師 前防衛大学校長・慶應義塾大学名誉教授 國分良成氏
講師 前防衛大学校長
慶應義塾大学名誉教授
國分良成氏
中国政治の研究を大学2年の時から始めて50年が経過した。しかし、中国には勝った者や権力者の正当性を書き記した文書しか残っておらず、「よくわからない」というのが中国研究者の共通認識であり、複数の客観的な根拠・経験値などを組み合わせて、常識をもって根拠ある推察をしながら中国研究を続けてきた。
中国の基礎知識
結党以来、中国共産党には次期後継者を決める制度がなく、党内民主主義はない。多くは、前任者が後任者を指名してきたが、恒例行事のように熾烈な権力闘争を繰り返してきた。
「中華人民共和国」の建国以後も、共産党の絶対的優位は変わらず、国家や政府の上に君臨し、憲法よりも優位性を保持したままの政治体制をとり続けている。また、軍拡の進む中国人民解放軍は共産党の軍隊であって、国家の軍隊ではない。
習近平体制をどう見るか
3期目に突入し、信頼できる部下だけを最高指導部に入れた。これまでは、権力基盤を固めるための、権力闘争の10年間であり、ここからが習近平時代の本当の始まりと言える。
米中関係と台湾問題
米国は、オバマ政権まで続いた対中関与政策が、トランプ政権で大きく変わり、中国に裏切られたという感覚が相当強い。
中国は台湾問題に関しては、平和統一を原則としているが、武力使用を放棄していない。武力行使に関しては、最後は習近平の「思惑」次第である。
日本の立ち位置はどうあるべきか
「戦略的互恵関係」が昨年の日中首脳会談で改めて確認された。建設的で安定的な日中関係の構築を双方の努力で進めていくことが重要である。
軍拡の進む中国に対処するには対話と抑止が重要であり、今こそ外交力が重要である。
日米関係については、大統領選挙後を見据えた幅広い関係・人脈構築が大切であり、日本のできること、できないことの明確な説明が必要である。
日本の課題は、安全保障についてはブームでなく、平時からの努力が必要。また、自衛隊をサポートするための国民的議論が必要である。さらに、魅力ある強い日本を築いていくためには、人材の育成と経済力の強化が急務である。
表彰式
全国防衛協会連合会は、当連合会の目的達成に率先尽力するとともに組織の拡大強化に努め、当連合会の使命達成と発展に尽力され、その功績顕著な14名に表彰状、1団体に感謝状を授与した。表彰式には、代理を含め10名が出席された。
受賞者(敬称略) ※青太字は出席された方々
【表彰状:個人】
井山 忠(北海道)
(故)柳原敏之(北海道)
屋代 美香(宮 城)
中泉松之助(秋 田)【代理 中泉 松司】
谷澤 誠(埼 玉)
栁田 茂大(長 野)
加来 武男(静 岡)
高垣 博(大 阪)
家次 恒(兵 庫)
平石 元治(徳 島)
松井 勝也(香 川)
城戸猪喜夫(愛 媛)
岡村佐致子(佐 賀)
鳥越 輝幸(長 崎)
【感謝状:団体】
㈱こうりょう(長 野)【小林 秀気】