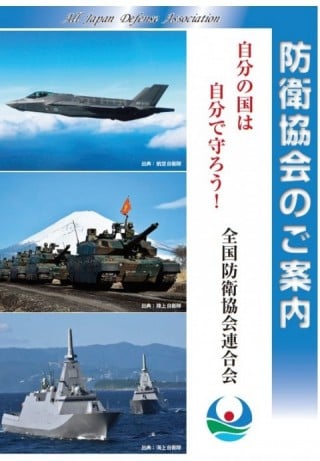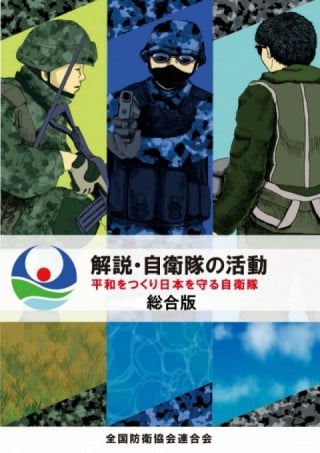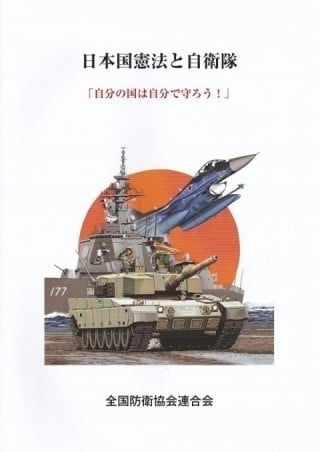防衛大学校教授による現代の安全保障講座
令和5年度 防衛大学校教授による「第29回現代の安全保障講座」
国際人の教養としての軍事学、日本の安全保障と軍事科学を学ぶ講座として、全国防衛協会連合会は、令和5年12月12日(火)グランドヒル市ヶ谷において、防衛大学校教授による「第29回現代の安全保障講座」(後援:防衛省、協賛:防衛大学校同窓会及び〔公財〕防衛大学校学術・教育振興会)を開催した。
主催者を代表して金澤博範理事長が挨拶した後、防衛大学校 電気情報学群 情報工学科 佐藤 浩准教授、人文社会科学群 国際関係学科 佐々木智弘教授の順で講義が行われた。
当日は防衛協会会員を始め、防衛省関係者、企業及び予備自衛官補等、約80名が聴講した。
【なお、講座内容の詳細については、冊子にして令和6年3月31日付で発行し、全国防衛協会連合会会員及び関係先に配布した。】
第1講座
『AIは戦争をどう変えるか?』
准教授 佐藤 浩氏
人類の歴史は戦争の歴史である。現在、確認されている最初の戦争は、1万5千年前の旧石器時代に スーダンで発生したものである。それから現在まで、戦争は絶えることなく続いているが、その様相は その時代における科学技術に大きく依存する。スーダンで使われた槍と矢から、鉄器、火薬、化学兵 器、核兵器と発展していく科学技術は、戦争のやり方をそれまでとは根本的に変えてしまう。 この革新的な科学技術の列に新たに加わろうとしているのがAI(人工知能)である。近年のAIの発展は 凄まじく、従来不可能であろうと思われてきたことが次々と実現されている。本講演では、戦争と科学 技術の歴史を踏まえ、今後AIがどのように戦争で使われるのか、またどのように戦争を変えていくのか について解説した。