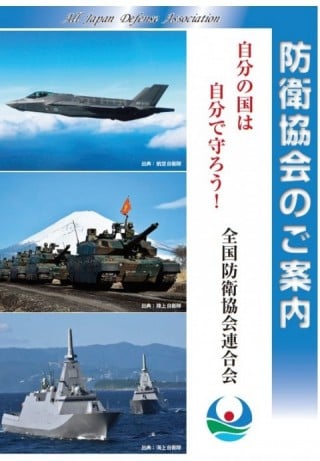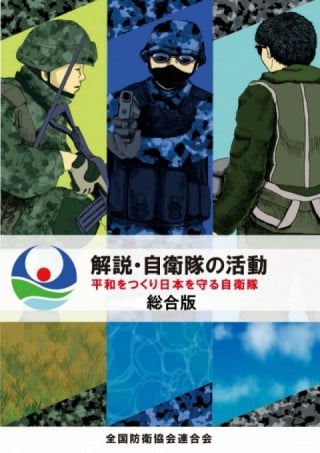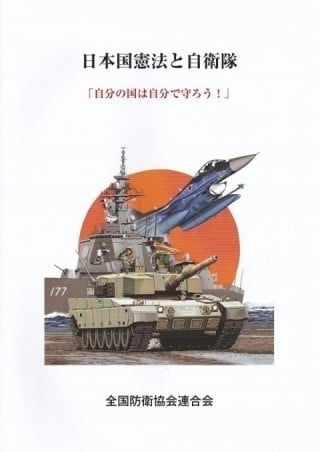一筆防衛論
令和6年
常任理事 伊藤 俊幸 防衛協会会報第166号(6.4.1)掲載
災害対処に対する誤解
能登半島地震の「救助」などに対する政府や自衛隊に対する批判は、「防災士」でもある元自衛官の筆者から見ると、知識不足で的外れなものだらけでした。
防災の責任者は県知事
防災、つまり災害を防ぐ方法は、「自助」(自分の命は自分で守る)、「共助」(地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ)、「協働」(市民、企業、自治体、防災機関等が協力して活動する)が原則です。そして防災士は、社会の様々な場において、防災力を高める活動をすることが期待されている人です。防災士になるためには試験と実地訓練を受け、「防災に関して一定の知識・技能を習得した」と日本防災士機構で認証してもらう必要があります。
さて皆さんは、防災における「救助」の責任者は誰だと思いますか?実はその責任を負うのは「都道府県知事」なのです。これは「災害救助法」で定められており、都道府県知事には、平素から、「必要な計画をつくり、強力な救助組織を確立し、労務、施設、設備、物資及び資金の整備」することが義務づけられています。
総理は県知事を支援する立場
つまり「協働」の中心は総理や自衛隊ではなく、総理は「資金」を、自衛隊は「機動力」をもって県知事を支援する立場なのです。平素からトラック協会等と協定を締結し、警察・消防を保持している県こそが「救助」のメインプレーヤーなのです。ちなみに、防災士の教科書である「防災士教本」には自衛隊に関する記述は一か所しかありません。
資金についても被災当初、「予備費47億円は少ない」という野党の批判がありましたが、これは復旧や復興という発災後数週間後に使用するための費用ではなく、発災直後の避難所へのプッシュ型支援などに必要な費用でした。総理は「熊本地震など、過去の倍の金額」と説明されたのですが、理解不足からか野党やマスコミから「こんな金額で復興できるわけがない」と間違った批判を繰り返しました。
統合任務部隊指揮官とは
また「自衛隊の災害派遣」も、基本的には「都道府県知事から要請」され、「緊急性・公共性・非代替性」があると自衛隊が主体的に判断して派遣するものです。阪神淡路大震災の反省から「市町村長からの要請」や「自衛隊の自主派遣」も可能になりましたが、いずれにしても県や市など自治体と調整することなく、自衛隊だけで勝手な行動がとれるわけがありません。
今回のような大規模災害の場合には、陸上自衛隊の方面総監が統合任務部隊指揮官として、人命救助・生活支援・復旧支援などの任務の執行が防衛大臣から委任されます。つまり総理や防衛大臣は、救助や災害対応を直接指揮するのではなく、同指揮官の判断をモニターするという関係になります。現場の詳細な状況や実動部隊のことも知らない政治家が、東京の指揮所でマイクロマネージメントしたら現場は大変なことになります。
1月1日・2日の実際の活動
1月2日以来、防衛省はHPで自衛隊の災害派遣の状況を毎日公表しています。16:10、発災。16:30、空自千歳基地第2航空団のF15×2機を「自主派遣」、「情報収集」を開始。被災地にある空自輪島分屯基地(レーダーサイト)は40名を「自主派遣」、近隣住民の「救助」にあたり約1000名を基地内に収容。
16:45、石川県知事は、石川県を管轄する第10師団長(名古屋市守山)に「災害派遣を要請」、自衛隊は、石川県庁4人、輪島市1人、福井県庁4人、富山県庁2人の「連絡官」を派遣。以後「情報収集」「人命救助」に加え、「輸送支援」「給水支援」を開始。
1月2日10:40、防衛大臣は陸自中部方面総監を長とする「統合任務部隊」を編成(陸海空自衛官1万人態勢)
戦力の逐次投入は当然の判断だった
東日本・熊本地震との一番の違いは、被害場所が過疎地だったことです。発災直後に来た津波や頻発した余震により、能登半島北部を東西に走る唯一の道路は破壊され15か所の孤立集落ができました。
輪島市から100km南に存在する石川県庁(金沢市)はほとんど被害がありませんでしたが、遠距離であるが故に、現場の状況把握は非常に困難でした。その更に約10km南に所在する陸自金沢駐屯地1400名の隊員には被害現場の知見がありませんでした。
県庁に派遣した「連絡官」からの日々の報告を踏まえ、統合任務部隊指揮官は、自衛官の安全を考慮し、二次災害が起きないように、現場に逐次投入しました。航空機等による空からの情報収集だけの結果だけで、機動力をもって大量の自衛官を現場に投入することはできません。
自衛隊の本来任務は「国防」
同時期に行われた習志野の空挺部隊の演習を批判し、「なぜ空挺部隊を現場に投入しなかったのだ」というマスコミなどによる批判は、本末転倒の議論といえましょう。自衛隊の本来任務は、「国防」です。自衛官が「事に臨んでは危険を顧みず」、つまり命の危険を顧みず完遂すべき責務とは、「国防」だけなのです。災害派遣という「支援」活動に、命を投げ出せという批判は、無責任極まる暴論といえましょう。