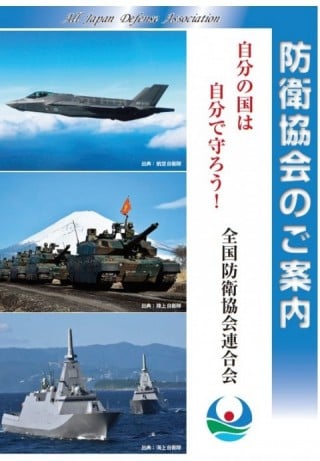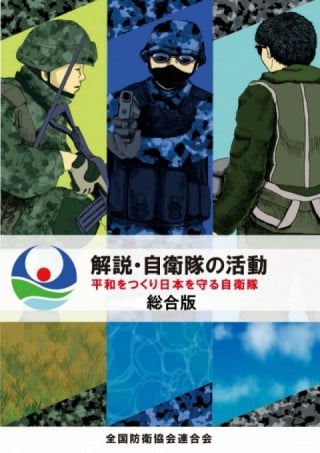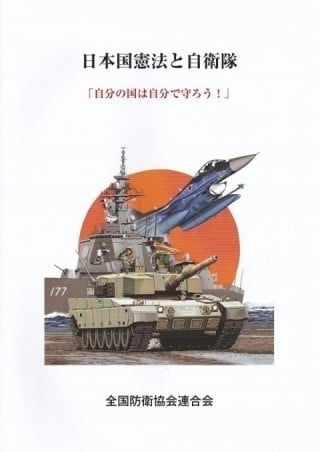「令和6年能登半島地震」による災害により、被害を受けられた皆様に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。
【ご協力・協賛】
全国防衛協会連合会では、当協会の活動の趣旨にご協力・賛同いただける企業様・事業者様を対象に、当協会ホームページのトップページへのバナー広告掲載を募集しています。ホームページをお持ちの企業や事業者の皆様、PRやイメージアップのため、ぜひご検討ください。
また、4半期に1回発刊の会報紙「防衛協会報」への広告掲載も募集しております。
詳細は、全国防衛協会連合会事務局にお問い合わせください。
☎03-5579-8348
✉ jim@ajda.jp
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |